赤切符というと、車やバイクに乗る人が対象のものと考えている人が多いでしょう。しかし実は、自転車でも違反の内容によっては赤切符を切られることがあります。赤切符とは正式には「交通切符(赤)」と呼ばれ、反則金による処理ではなく、刑事事件として検察に送致される重大な交通違反に対して交付されるものです。つまり、赤切符は「犯罪行為として扱われる違反」に対して発行されるもので、場合によっては裁判所での略式裁判を経て罰金刑が科されることもあります。
自転車は法律上「軽車両」という扱いになっており、道路交通法の対象になります。これは、歩行者とはまったく異なるルールで運用されているということを意味します。たとえば、車道の左側通行、信号機の遵守、歩行者優先の原則など、軽車両として守るべきルールが多数存在します。自転車だからといって「多少のことは大丈夫」と思っていると、思わぬ形で赤切符を切られてしまうリスクがあるのです。
特に、警察はここ数年、自転車の危険運転に対する取り締まりを強化しています。都市部では取り締まりの重点エリアが設定されていることも多く、違反した場合はすぐに赤切符の対象となることもあります。自転車は気軽な移動手段である一方で、法的責任は軽くないという現実を、まず理解しておくことが大切です。
自転車の赤切符の対象となる主な違反行為とは
自転車による赤切符の対象となる違反には、いくつか代表的なものがあります。まず代表的なのが「信号無視」です。信号無視は、自転車利用者が日常的に犯しがちな違反でありながら、重大な交通事故を招く原因でもあります。車両の進入する交差点で信号を無視して進入すれば、歩行者や他の車両との接触事故が発生しやすく、その危険性は極めて高いのです。
次に「酒気帯び運転」も大きな問題です。多くの人が「自転車なら飲酒運転しても大丈夫」と思いがちですが、これは完全な誤解です。道路交通法第65条では、車両(軽車両を含む)を酒気を帯びた状態で運転することを禁止しており、これは自転車にも完全に適用されます。実際に、自転車で酒気帯び運転をして赤切符を切られたという事例は少なくありません。
また、「一時停止無視」「踏切での停止無視」「通行禁止の歩道への進入」「無灯火走行」なども対象になります。特に夜間の無灯火は、歩行者との衝突事故に発展しやすく、摘発件数も多くなっています。さらに最近では「ながらスマホ運転」や「イヤホン着用走行」といった、注意力の低下を招く行為も取り締まりの対象とされており、場合によっては赤切符が交付されることもあります。
これらの違反行為は一見軽く見えるかもしれませんが、事故のリスクを高め、他人に重大な損害を与える可能性を持っています。そのため、警察も厳しく対処しているのが現状です。
実際に赤切符を切られるとどうなる?その後の流れを知ろう
もしも自転車での違反行為によって赤切符を切られた場合、そこからは交通違反としてではなく、刑事事件としての対応が始まります。まず、違反の現場で警察官に停止を求められ、違反内容の説明を受けた上で赤い色の切符が交付されます。これは正式には「告知書」と呼ばれ、署名を求められることもあります。
その後、数日から数週間のうちに「出頭通知書」が自宅に届きます。これは、地元の検察庁または家庭裁判所に出頭して供述を求められるものです。そこでの供述調書に基づいて検察官が処分を決定します。通常は略式起訴となり、地方裁判所での略式裁判で罰金が言い渡されます。
罰金の額は内容にもよりますが、数万円から十万円以上になるケースもあり、決して軽い処分ではありません。また、罰金刑が確定すると「前科」として記録されるため、重大な問題に発展することもあります。さらに、未成年者の場合でも例外ではなく、保護者の同伴が求められ、教育的措置として家庭裁判所に送致されることもあります。
また、赤切符を受けた場合、その記録は一定期間残り、将来的な違反や事故の際にも影響することがあります。これは、自転車という日常的な手段が、場合によっては重大な法的トラブルの引き金になるという現実を示しています。
赤切符が記録されると前科になるのか?
赤切符が交付され、それに伴って略式裁判で罰金刑が確定した場合、その行為は「前科」として扱われます。ここで注意したいのは、「罰金=軽い処分」と考えるのは誤りであり、法的には立派な刑罰であるという点です。略式起訴によって課せられた罰金刑も、刑事事件として記録されるため、法務局や警察のデータベースに残ることになります。
前科があるからといって日常生活のすべてが制限されるわけではありませんが、一部の職業や資格、留学、海外渡航などにおいて、申請時に不利益が生じる可能性は否定できません。特に、就職活動や公務員試験などでは、過去の違反歴や前科が問われることがあるため、自転車の違反が思わぬ形で将来に影響を与えることもあるのです。
また、前科があると次回以降の交通違反においても厳罰化されやすくなり、検察や裁判所の判断に影響を与えることもあります。一度の過ちが今後の法的立場に影響を及ぼすという点を理解し、日常の中で「違反をしない意識」を持つことが重要です。
自転車での違反を防ぐために知っておきたいルール
自転車に乗る際に守るべきルールは数多くあります。最も基本的なのは「車道左側通行の原則」です。多くの自転車利用者が歩道を当たり前のように走っていますが、実はこれは例外的な措置でしか認められておらず、基本的には車道の左側を通行しなければなりません。歩道を通行する場合でも、歩行者優先が絶対原則であり、スピードを出したり、ベルを鳴らして歩行者をどかすような行為は法律違反です。
信号無視、酒気帯び、ながらスマホ、イヤホンなども自転車の重大な違反として取り締まり対象です。近年では、信号のない交差点での「止まらずに進行」しただけでも一時不停止として違反切符が切られることがあります。こうした細かい点も含め、今一度、自転車に関する交通ルールを見直すことが、自分自身を守ることにつながります。
また、防犯登録やヘルメット着用の義務化(地域により努力義務)など、法整備も進んでいます。自転車保険への加入も義務化が進む中で、自転車に乗るという行為が「車両としての責任を持つこと」だという意識を、日頃から持つことが大切です。
自転車に乗る人の責任と自覚が求められる時代へ
自転車はかつての「子どもの乗り物」から、通勤通学、買い物、配達業務など多様なシーンで活躍する社会的な交通手段へと進化しています。それに伴い、法的な扱いも変化しており、自転車利用者にも運転者としての責任と自覚が求められるようになりました。
現代では、自転車事故の被害額が数千万円にのぼる事例も報告されており、加害者となった場合は重大な民事責任を負う可能性があります。自転車保険への加入が義務化されている地域も増え、リスクに対する備えが当たり前の時代となっています。
それでもなお「ちょっとくらいなら」といった意識で違反行為をする人は少なくありません。しかしその「ちょっと」が取り返しのつかない事故やトラブルにつながり、自分や家族の人生に大きな影響を及ぼす可能性があるということを、ぜひ多くの人に知ってほしいところです。
まとめ:自転車でも赤切符は現実、ルールを守って安全に
自転車で赤切符を切られるというのは決して特別な話ではなく、誰にでも起こり得る現実です。信号無視や酒気帯び、ながらスマホといった行為は、自転車でも重大な違反とみなされ、刑事処分の対象となります。赤切符は交通違反の中でも最も重い処分のひとつであり、将来的に前科として記録されるリスクも伴います。
日頃から正しい交通ルールを理解し、守ることが、自分自身の安全だけでなく、他人への思いやりにもつながります。自転車は便利で快適な移動手段であると同時に、法的責任を伴う「車両」であることを常に意識し、事故や違反を未然に防ぐ行動を心がけましょう。
自転車の処分にお困りの方はREYCLE CYCLEへ
REYCLE CYCLEでは、ご不要になった自転車を買取または無料でお引き取りいたします。お気軽にご相談ください。
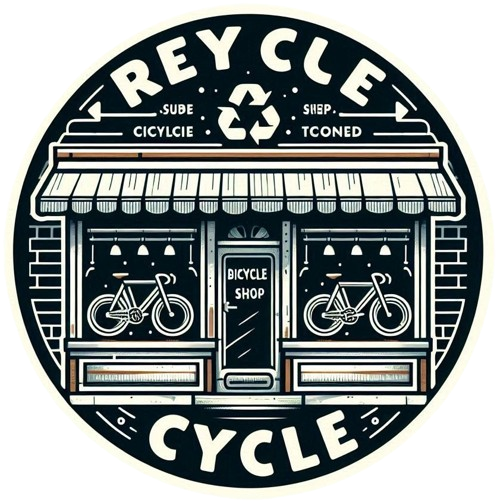








コメント